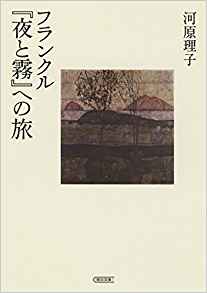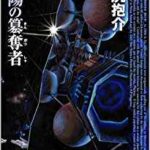今作は、世紀のベストセラー『夜と霧』(フランクル)について書かれたもので、朝日新聞連載の「ニッポン人脈記」が纏められ、新たに文庫化されたものだ。
著者の河原理子さんは、東京大学文学部を出て、朝日新聞に入社し、記者を長年されていた方。雑誌『AERA』の副編集長なども務めている。
性犯罪の取材などをきっかけに、犯罪被害者への傾聴をされており、そこから、究極の人間悪(ホロコースト)と対峙したドイツの精神学者フランクルの著作と向き合っている。
フランクルの『夜と霧』への賛辞は、すでに語り尽くされているといった所だが、人として、特に日本人としては、やはり読んでおくべき一書だと思う。
僕自身、昭和54年の生まれとして、バブル崩壊後の “どっちらけの日本社会” を生きて来たわけだが、第二次世界大戦からの日本民族の在り方を思う時、ナチスドイツの蛮行に目を向ける事が、そのまま、戦後の日本という国に生きている自身の、人生に対する何かの答え探しの一端を示してくれるような気がしてならない。
フランクル自体は、アウシュビッツでの残虐な行為を描くといったセンセーショナルなメッセージを書いたわけではなく、あくまでもホロコーストという極限の状況の中でも輝き続けた、人間の魂の尊厳や、誰人も奪う事の出来ない良心を、書き残したわけだ。
そのような、フランクルの思想のあり方が、現代日本の数知れない病巣に必要な考え方だと、河原氏は随所で訴えている。
・世田谷一家殺害事件で、突然家族を失った方の不条理な運命へのやりきれなさ。
・秋葉原通り魔事件で、派遣社員の男性の、社会やインターネット上の相手への理不尽な恨みと行動。
・東日本大震災で、突然命を奪われた数多くの方々。
そのような、不条理な死というものへの捉え方を、宗教を拠り所とせずに、考えるきっかけに本書はなる。
“人格の尊厳と利用価値を混同してはならない”というフランクルのメッセージを、河原氏は救い上げており、印象に残った。
何か、生殺与奪の方法が、利用価値や、その人の生産性のようなもので計られ、
ただ生きてあるだけの事、その事に対する、うしろめたさや、言い知れぬ罪悪感のようなものを、社会全体が、無言のうちに共有してしまっているのではないか。
その、無言の重圧に耐えかねた者は、犯罪へと走ってしまうし、自殺へと自身を追い込んでしまう。
日本一の納税者の死も、有名人の死も、一庶民の死も、障碍者の死も、同じく等しいものであるべきだ。
死そのものさえも商売となり、序列が出来てしまっている日本社会のひずみ(これは日本仏教界の腐敗堕落へと繋がっているのだが)。
そして災害により、多くの命が一瞬で奪われる不条理。
あらゆる不条理な死というものに対して、また皆が等しく受ける死というものへの心構えとして、
それでも、生きているこの瞬間はかけがえのない美しいものだ。という観念ではない感動。
誰もが持っている苦しみや不安への回答として、今なおフランクルの『夜と霧』が読まれ続ける理由なのかもしれない。
河原氏の綿密な取材は、フランクルの足跡や、場面分析、周辺人物への考察など、新聞記者らしい緻密な構成。
『夜と霧』の隣に置いておきたい、思想の横断の旅路だ。
※本書に出てくる映像資料などの情報をアーカイブ的に貼っておきます。
映画『夜と霧』⇒1956年に制作されたドキュメンタリー。フランクル原題は『一心理学者の強制収容所体験』だが、発刊当時ヒットしていた別のフィルムタイトルを本のタイトルとした。
NHK 映像の世紀 ブーヘンヴァルト強制収容所
「ブーヘンヴァルトの歌」
⇒歌詞の中で “私たちはそれでも人生にイエスと言おう” と歌われる。フランクル思想のひとつの結論だ。
「テレージエンシュタット ユダヤ人居住地の記録映画」
⇒ナチスによるでっち上げのプロパガンダ映画をモチーフに近年映画した作品『偽りの楽園』
「Viktor & I」
⇒フランクルのお孫さんが作成したドキュメンタリー映像。