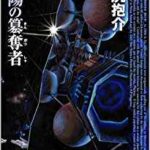シモーヌ・ヴェイユとは、1909年生まれのフランスの哲学者である。彼女の透徹した社会的抑圧への原因究明と、それに抵抗する思想を表した『自由と社会的抑圧』に、1200年代の日本の僧侶、日蓮との類似性を読み取る事が出来たので、ここに拙文を記しておく。
シモーヌ・ヴェイユとは、1909年生まれのフランスの哲学者である。彼女の透徹した社会的抑圧への原因究明と、それに抵抗する思想を表した『自由と社会的抑圧』に、1200年代の日本の僧侶、日蓮との類似性を読み取る事が出来たので、ここに拙文を記しておく。
シモーヌ・ヴェイユの思想の特徴は、第一次世界大戦を前後とした祖国フランスが全体主義、軍国主義に傾いて行った時代の中で、強固なまでに平等主義・自由主義をかかげた点にある。また、国家権力によって、国民ひとりひとりの自由な思想、行動が制限され、国民の生命が国家への隷属を強いられる事への抵抗と、その原因の探求が主である。
 1222年に鎌倉時代に生まれた日蓮は、封建社会が根強い当時の日本において、飢饉や疫病が蔓延し、苦しみに満ちていた民を憂い、その根本悪の原因が権力者の統治力の不備と、誤った信仰心にあることを指摘しながら、生涯にわたり時の権力者に諌暁を続けた。
1222年に鎌倉時代に生まれた日蓮は、封建社会が根強い当時の日本において、飢饉や疫病が蔓延し、苦しみに満ちていた民を憂い、その根本悪の原因が権力者の統治力の不備と、誤った信仰心にあることを指摘しながら、生涯にわたり時の権力者に諌暁を続けた。
権力悪との闘争という点に、ヴェイユと日蓮の類似を見る。
ヴェイユの1934年の論考『自由と社会的抑圧』の序文において
“現代とは、生きる理由を通常は構成すると考えられている一切が消滅し、すべてを問い直す覚悟なくしては、混乱もしくは無自覚に陥るしかない、そういう時代である”
と述べているが、自身の時代を取り巻く思想が、自身と人間そのものにとって本当に幸福をもたらすのかどうかとの問いをすべきであるという。
同じように日蓮は、鎌倉時代の日本において、権力者が念仏などの既成仏教を利用し民衆を統治する中で、四箇格言と呼ばれる既成仏教批判を宣言し、権威を笠にきた諸宗の僧侶たちに、思想界においての宣戦布告を行った。
ヴェイユにせよ、日蓮にせよ、思索の動機は民衆への同苦であり、民衆の幸福を実現しえない既成の思想への憤りであり、民衆の精神解放へのやむにやまれぬ感情の発露からだ。
先鋭的な思想家の多くが、宣戦布告を行った瞬間から既成概念からの弾圧を受け続ける。
ヴェイユ『自由と社会的抑圧』の結には、
“かかる道程に踏み出す人間は、間違いなく精神的な孤独と周囲の無理解を覚悟せねばならず、確実に既存秩序の敵対者からも奉仕者からも敵意を招くだろう”
ヴェイユ自身の生涯が34歳で閉じられるまで、まさしく民衆解放への闘争の連続であった。同じく日蓮は、自身の説く妙法を世に弘めれば三類の強敵が必ず出現すると述べている。
ヴェイユのいう、既存秩序の奉仕者とは資本主義であり、既存秩序の敵対者とは当時ロシアを中心にその勢力を拡大していたマルクス主義であった。ヴェイユはそのどちらにも人間不在の違和感を覚えた。
『自由と社会的抑圧』の第一章・マルクス主義の批判において、
“いかなる技術が開発されようと、運用される機械設備を、己の額に汗して、絶えず更新し最適化する労苦から、人間が解放されることはあるまい”
とヴェイユは述べているが、マルクス主義・革命家たちの標榜するユートピアへの冷笑ともとれる。マルクス主義の批判においてヴェイユの論調は一貫しており、機械化やオートメーションそのものが、人間の創造力の制限になるとの指摘をしている。
日蓮は時の権力者に提出した立正安国論において、
“謗法の人を戒めて正道の侶を重んぜば、国中安穏にして天下泰平ならん。”
と、記している。民衆の生命力を奪う“謗法の人”(正しい教えに背き自分勝手な考え方に執着する人)を用いず、人間の生命力を横溢させる正道(妙法)を用いることで、国を安穏にせよとの諫言であった。
どこまでも人間一個人の生命力の開花を希求したのは、日蓮、ヴェイユ共々に同じであった。
またヴェイユは同じく、革命というものを次のように論じている。
“革命という語は、それが為に人が殺し、それが為に人が死に、それが為に人民大衆が死に追いやられるにもかかわらず、いっさいの実体を欠く語なのである”
マルクス主義者に見られる過度な革命への闘争は、結局は人民そのものを傷つける事になってしまう。人民の幸福を願いながらも、人民そのものが死や戦争という不幸を被る事への矛盾と憤りをヴェイユは感じていたのであろう。
続いて、ヴェイユは『自由と社会的抑圧』の第二章・抑圧の分析において、宗教的権威と官僚主義への批判を、次のように強めている。
“特権者は、生きる為に他者の労働に依存しつつも、自身が依存する当の人びとの運命を掌握する。かくて平等は消滅する。自然と和解する宗教的儀式が、数人の祭司のみが知る秘密となり、やがては専有物となった時である。この占有者が科学者や技術者を名乗っていようと、なんら本質は変わらない”
“ある程度の複雑さに達した調整は数人の指導者の専有物となる。その結果、ものごとを遂行するさいの第一の掟は服従となる”
このような構造は、それが宗教であれ、社会構造であれ、人間社会の病巣として、現代にも根強く横たわっている。
16世紀に行われたルターの宗教改革に至る時代背景などはその最たる史実であり、キリスト教の権威をもった司祭が免罪符を使い信徒を隷属させたが、その構造は日蓮が対峙した宗教的権威と同等であった。当時の日本の宗教界は、宗派を問わず僧侶に民衆を隷属させる思想が一般的であり、本来の万人平等を説く日蓮は他宗の僧侶たちから一斉攻撃を浴びた。
そのような人間精神の病巣を見抜いていた日蓮は、万民に平等たる信仰の対象物として“御本尊”を書き顕し万民平等を実現する方途を示した。
ヴェイユは、“この占有者が科学者や技術者を名乗っていようと、なんら本質は変わらない”
と語っているが、それが宗教の世界でなくとも、すべての社会構造において、官僚と呼ばれる者たち、若しくは、官僚的役割を担う者たちの、自己の権威付けの余念のなさは、いつの世も変わらない。ヴェイユの考察した、社会的抑圧の本因はこのような一部の特権者たちによる権威的精神風土であり、それに抗する力を持てない人間自身の内面に向けられているように思えてならない。
これをヴェイユは“人類の本質的な悪”として第二章において次のように述べている。
“人類の本質的な悪、すなわち手段による目的の代置が出現する。ときには戦争が、ときには富の追求が、ときには生産が前景にあらわれるにせよ、悪そのものは変わらない”
ヴェイユが示した人類の本質的な悪を、日蓮は仏法上の法理から“第六天の魔王”と定義した。人間生命に本来具わる働きとして、他人を自身の手段にしたいという欲望(他化自在天)があり、その自己の生命をコントロールする方法として、日蓮は妙法蓮華経を説いた。
民衆を目的遂行の為の手段としてしか見ない“人類の本質的な悪”へ抵抗する方法としてヴェイユが希求していたものが、日蓮の思想に含まれていた。
『自由と社会的抑圧』の第三章・自由な社会の倫理的展望の冒頭において、ヴェイユは次のように高らかに宣言をしている。
“自分は自由たるべく生をうけたと人間が感じることを、世界のなにものも妨げることはできまい。断じて、なにがあろうと、人間は隷属をうけいれられない。”
これは隷属をさも道理のように錯覚させようとする働きに対する、人間生命の魂の尊厳の宣言とも言える。隷属を強いる生命の働きを第六天の魔王とした日蓮は、辧殿尼御前御書にて、次のように述べている。
“第六天の魔王十軍のいくさををこして法華経の行者と生死海の海中にして同居穢土をとられじうばわんとあらそう、日蓮其の身にあひあたりて大兵ををこして二十余年なり、日蓮一度もしりぞく心なし”
権力者、若しくは全人類の生命に内在する、第六天の魔王との、精神世界における戦闘を日蓮は一度もしりぞく心なく行っていた。そのような純潔なる生命の闘争はヴェイユのそれと深く共鳴する。
また、仏法では生命に内在する第六天の魔王の働きを無明と呼び、またそれに打ち勝つ生命の働きを仏性と呼ぶ。日蓮が書き顕した御本尊を縁として、自己の善性(=仏性)を顕在化していく中で、民衆は第六天の魔王の呪縛から解き放たれるのだと言う。
それに類似したヴェイユの第三章の論考にこのようにある。
“思考と肉体のあらゆる潜勢力を動員せずにはなにひとつ得られないという事実自体が、人間にとっては、情念のやみくもな支配から完全に身をひきはがす誘因をなす。ほかならぬこの明晰な見解こそが、節制と勇気の徳を生むのであり、これらの徳を備えていない生など、恥ずべき錯乱でしかない。”
ここでヴェイユが述べている、
“情念のやみくもな支配”とは日蓮がいうところの“無明”の事であり、
“節制と勇気の徳”とは“仏性”の事ではないだろうか。
続き、ヴェイユの思索は、集団に埋没せず、個から社会をかえていく日蓮に接近している。
“大海に呑まれる一滴の水と同じく受動的に社会にひきわたされるのをやめるには、人間のほうで社会を熟知し、社会に影響をおよぼす必要がある。個人は集団を凌駕する。ひとりで自己とむきあう精神においてのみ思考は形成されるからだ”
と第三章で述べている。
つづき、ヴェイユの論考は一つのユートピアの形を模索していく。
“比類なき歓びと充溢の瞬間に、真の生が現前することを瞬時に知り、世界が存在し、みずからが世界にあることを全身で感じる。すぐれて人間的な行為を構成するにいたるとするならば、そのような文明からはどれほど驚嘆すべき生の充溢を期待できるだろう。”
ここに至っては、ヴェイユの思考は宗教的概念へと深まっている。“みずからが世界にあることを全身で感じる”とあるが、仏法思想の九識論との共鳴をみる。
九識論とは人間生命の意識から無意識に至る深度を段階的に論じたものであるが、その最深識を阿摩羅識とよび、宇宙生命の根源実在を解き明かしている。この根源からの生命力の充溢を根本とした平等な社会構成こそ、日蓮の希求した世界に他ならない。
またヴェイユは次のようにも論考をしている。
“生存の各瞬間は各人にとって、万人がいかに深くお互いにひとつに結ばれているかを、理解し実感する機会となろう。なぜなら、だれもがみな類似する障碍に同じ理由から対処せねばならないからだ。そのときあらゆる人間関係は、もっとも表層的なものから愛情に満ちたものまで、仲間を結びつける力強い友愛に似たなにかに変わるだろう”
万人が深くお互いにひとつに結ばれているかを実感する方法として、日蓮は御本尊への帰依と題目の修行を述べており、生死一大事血脈抄に次のようにも記している。
“自他彼此の心なく水魚の思を成して異体同心にして南無妙法蓮華経と唱え奉る処を生死一大事の血脈とは云うなり”
水と魚の関係のように、人間同士が相互に信頼関係を築き、助け合い、友愛に満ちている世界。ヴェイユの希求したユートピアと日蓮のそれはここでも合致をみる。
『自由と社会的抑圧』の第四章・現代社会の素描においてヴェイユの社会への視線はより鋭利な刃物のごとく、病巣をえぐりだしている。
“経済闘争は競合ではなく一種の戦争になったかにみえる。労働を手際よく組織する以上に、株式を売りさばいて、社会内に散在する流通可能な資本をできるだけ大量に奪いとり、生産物を売りさばいて、各所に散逸した金銭をできるだけ大量に奪いとる、これが肝要である。投機と宣伝を梯子に、いっさいが臆見の領域、虚構とさえいえる領域で演じられる”
とあるが、アメリカ資本主義への警鐘ともとれる。また、それに追随する日本経済の袋小路をも予見していたと言っても過言ではない。ヴェイユは明確なまでに、資本主義、社会主義の矛盾をつき二大思想の激突となる第二次世界大戦勃発前夜に、それらのどちらにも依存しない第三の文明を希求していた事になる。
また現代社会の隷従の構図としてヴェイユはこのようにも述べている。
“隷従は当人にこれを愛させるまでに人間の品性を損なう。さらに、現実に自由を享受する人間でなければ、自由を貴重なものと思わない。非抑圧者と抑圧者の別なく、従属するすべての人間をおのれの似姿とすべく造形する。”
“大新聞やラジオをもってすれば、朝食や夕食といっしょに、できあいの愚かしい臆見を全民衆に丸呑みさせられる。なぜなら、なんの反省もなく呑みこむ精神のなかでは、たとえ理にかなった見解でさえ、歪められて偽りとなるからだ。”
と述べているが、これらは、自身のアイデンティティを疑う術を持たない民衆への警告であるとともに、そのような民衆を作り出す事に余念のない権力者への警句に他ならない。
日蓮の民衆及び国家への洞察にも同じものを見る。日蓮は六波羅蜜経の文を引いて
“心の師とは・なるとも・心を師とせざれ”
と記している。これは「自身の心を律して自身が自身の師となる事は大切ではあるが、そもそも、自身はアイデンティティが不安定な民衆であり、国家の情報操作の餌食となっている自身であるからこそ、自身の心を、自身の師としては絶対にいけない」という、民衆に対しての慈悲からの警告であった。
その国家の情報操作に喘いで、全体主義へ傾く民衆の不幸の根を断つ手段として、日蓮は妙法蓮華経を示して見せた。
日蓮と同じくヴェイユは、民衆の不幸の根を断つ方法を、次の様に示している。
“今日、人間を愚鈍にする為のあらゆる試みには、強力な手段がいくらでも利用可能である。反対に最新の新聞論壇を駆使しても不可能な事がひとつある。すなわち、明晰な概念、的確な推論、合理的な判断をひろく普及させることだ。”
ここでヴェイユが述べている、“明晰な概念、的確な推論、合理的な判断をひろく普及させる”行動そのものが、日蓮の生涯を貫いていた精神性に他ならない。
日蓮は、当体義抄において、
“正直に方便を捨て但法華経を信じ南無妙法蓮華経と唱うる人は煩悩業・苦の三道・法身・般若・解脱の三徳と転じて三観・三諦・即一心に顕われ其の人の所住の処は常寂光土なり”
と論じているが、仏法上の法理の上から、人間に本来内在する明晰な思考能力が必ず顕現する事を述べている。どのような立場の民衆であれ、日蓮の示した妙法蓮華経を実践していくなかで、“明晰な概念、的確な推論、合理的な判断”を必ず得られるようになると説き、それを日蓮は“ひろく普及”させようとしていたのである。
ヴェイユと同時期の哲学者、牧口常三郎は思想弾圧にあった獄中から家族への手紙にこのように記している。
“カントの哲学を精読して居る。百年前、及び冥後の学者共が、望んで、手を着けない『価値論』を私が著わし、しかも上は法華経の信仰に結びつけ、下、数千人に実証したのも見て、自分ながら驚いて居る”
ヴェイユと日蓮に共通する“明晰な概念の普及”という行動思想を貫き、第二次大戦中の軍国主義と闘って牧口常三郎は獄死に至った。
ヴェイユは第四章の結びにこのように記している。
“自己及び、他者のうちなる人間的尊厳を尊重しようとする者に、何ができるというのか。われわれを打ち砕く機械の歯車装置にいくばくかの猶予をもたせ、わずかでも思考を呼びさます機会をあまさずとらえ、政治と経済と技術の領域で、社会組織が個人を囲い込む種々の絆の内部において、個人にいくらかの行動と自由をゆるす可能性のあるものすべてを奨励すべく力を尽くす以外に。”
中央権力者の思想統制が強固であった、当時のヴェイユを取り巻く状況の中で、極限的に発した答えのひとつが、まさにこれである。
そして、この答えを体現していたのが、700年前の日本の僧侶日蓮だった。
同じく『自由と社会的抑圧』の結において、ヴェイユはこう述べている。
“肝要なのは、個とみなされる人間に権利として帰属するものと、人間に逆らい集団に武器を与える性質のものとを切り分けて、後者にかかわる諸要因を抑制し、前者にかかわる諸要因を発展させようと努めることだろう”
ここでいう
後者の“集団に武器を与える性質のもの”とは日蓮仏法上の無明に値する部分であり、
前者の“個とみなされる人間に権利として帰属するもの”とは仏性に値する部分である。
日蓮仏法を基調とした行動とは、対話により相手の内発性を高め、無明を抑制し仏性を発展させる活動にほかならない。この行動そのものを日蓮は、相手の悪性を折り伏せ抑制させ、善性を高める行動という意味から“折伏”と定義づけた。
ヴェイユは本著の最後に、人類への希望としてこう記している。
“すなわちこの努力を行う人間は、われとわが身を狂気と集団的眩暈の汚染から救いだし、社会の差しだす偶像をみおろしつつ、自分の為に精神と宇宙との源初的協定をむすびなおすことができるだろうことを”
日蓮は当体義抄にこう記している。
“実教の法華経を信ずる人は即ち当体の蓮華・真如の妙体是なり”
シモーヌ・ヴェイユが本書『自由と社会的抑圧』で提起した、人間の根本悪への深い洞察とその抑制方法を、日蓮仏法に発見した思いだ。
2017 某日